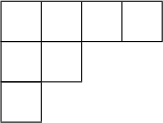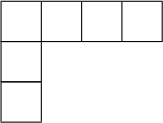ツイッターで大学新入生にオススメの数学書を、ハッシュタグ #新入生に勧める数学書2018 で募集しました。
タグを作りました。皆さん、自由に語りましょう。
— Loveブルバキ(ラブル) (@lovebourbaki) 2018年3月7日
いろんな立場の人が選ぶことで、楽しいリストができると思います。#新入生に勧める数学書2018#新入生に勧める物理学書2018
分野、理由も併記するといいでしょう。分野は数学史や伝記などもok、幅広くいきましょう。
皆さんのオススメの本を抜粋して紹介します。
参加してくださった皆様、ありがとうございました。
(ツイートの掲載は許可をとっています。了承していただいた皆さん、ありがとうございました。)
はじめに
こんな企画を始めたものの、知らない人が勧める本にすぐに飛びつくのではなく、著名な数学者が勧める本をまずは本屋で見て欲しいと思います。
それを知るには、ちょうど、毎年この時期に出る『数学ガイダンス2018』がオススメです。
数学者が勧める本の紹介や、数学の各分野の紹介、大学での勉強法などがまとめられています。
(とは言え、ツイッターで紹介してくださった多くの本は、この本でも紹介されています。)
数学ガイダンス2018 (日本評論社)
— ペーパー (@paper3510mm) 2018年3月7日
ここ何年か毎年出ている本で、大学に入ってする"勉強"とはどういったもので、大学での学びとはどうあるものなのかが、よくわかると思います
数学はもちろん物理の人にも読んでほしいですね#新入生に勧める数学書2018#新入生に勧める物理学書2018 https://t.co/mjZfFhkR8a
あと、個人的な意見を少し。
大学で使う教科書には、4年やそれ以上の長い期間使い続けることができるものがあります。
いわゆる名著と呼ばれる本や大学で勧められる本はそういうものが多いです。
最初は、自分で理解できるように平易に書かれた簡単な本を買いがちですが、そういう本は半年もすれば必要なくなることも多いです。
なので、是非とも長年読み続けられてきた名著を、最初は理解できなくても、買っておいて折にふれてチャレンジして欲しいです。
これは難しい本を読めと言っているのではないです。
また、もちろん自分で理解できる本から始めることも大事ですし推奨しますが、分かりやすさという基準では捕らえられない数学書の価値も知って欲しいところです。
あと、大学の図書館を有効活用して欲しいですね。
本を買うときは、本屋や図書館でちゃんと自分で見てからにしましょう。
一般
高校数学と大学数学ではギャップを感じることが多いと思います。そのギャップを埋めてくれる本や、数学の面白さを伝える本を見ていきましょう。
☆数学ガール シリーズ
論理記号とかε−δ論法とかは、『数学ガール』を読んだ方がとっつきやすいなぁと個人的には思うんです…。
— くろもみじ (@mathematica2357) 2018年3月7日
#新入生に勧める数学書2018
数学ガールで数学が好きになった人は多いようです。大学生でも読んだことがなければ是非とも読んで欲しいです。
たくさん本が出ていて何を買えばいいのか分からない場合は、以下のページを参考にしてください。
数学ガールはどれから読めばいいの?という方は、こちらをお読みください(^^)つ https://t.co/11rvnYV2kL pic.twitter.com/l7kG8WGNZc
— 結城浩 (@hyuki) 2018年3月11日
☆ オイラーの贈り物
#新入生に勧める数学書2018
— 🌟ちき🌟 (@chiki_fu) 2018年3月7日
数学書か分からないけどオイラーの贈り物は高校生でも楽に読める。文系でも読める。
文庫版もあるし。 pic.twitter.com/dxO58yi0IE
☆志学数学
『志学数学 -研究の諸段階 発表の工夫』伊原 康隆
— Loveブルバキ(ラブル) (@lovebourbaki) 2018年3月7日
数学に憧れを持った中高から、一流の数学者(!)になるまでの数学への接し方が書かれています。検索すると河東先生による書評もあるので参考にしてください。
正直、「絶対に」読んで欲しいです。https://t.co/8tnaFTdmOj #新入生に勧める数学書2018
この本は、本当にオススメです。
大学生に限らず、数学者や研究者に憧れている人や数学に興味がある人は是非とも読んでみてください。
☆数学の大統一に挑む
E.フレンケル「数学の大統一に挑む」
— げッドンがッくさばいボッば (@kyow_Q) 2018年3月9日
お話本です
一見全く異なって見える、整数、複素数、末には物理の世界を統一せんとする現代数学の野望を、卓越した数学者である著者が学生向けに平易に、そして情緒に満ちた語り口で綴る至高の一冊です
要はサイコーなのでマジで読んで#新入生に勧める数学書2018
数学の最先端を知ることができる本はなかなかありません。
いろんな概念を出来るだけ易しく解説しているので、すべて読み通すのは難しいかもしれませんが、是非とも手にとって読んで欲しい本です。
微積分
微積分は名著と呼ばれる和書が多いです。
以下の高木、小平、杉浦の三冊のうち気に入ったものを買っておいて損はしないと思います。
☆解析概論
善きにつけ悪きにつけ高木貞治の洗礼を浴びることは、大学に入りたての時には意味あることだと思う。
— しょすたこおびち (@fredholm_eq) 2018年3月7日
手に入れてから30年経ってボロボロになったけれど、未だ開いて読むことがある。「解析概論」#新入生に勧める数学書2018 pic.twitter.com/250N4Mszdv
「取り敢えず、高木貞治さんの解析概論を読んでおけば微積の授業で困る事は無くなるはずです!」
という意見もありました。
著者の高木貞治は近代日本数学の父とも呼ばれています。
昔から長年読まれ続けてきた本であり、一番有名な数学書だと思います。
実はそれほど難しいわけでもないですが、新しい本に比べると書き方の面で読みづらいかもしれません。
☆解析入門I II (杉浦光夫)
東大出版の解析入門I,IIおよび解析演習
— すむーずぷりんちゃん🍮 (@mat_der_D) 2018年3月7日
基礎的な微積から複素解析やベクトル解析まで扱っている本です。
高校時代に微積が好きで好きでたまらなかった人におすすめします。
「ちなみに」な情報が多いので、うんちく好きな人にもオススメです。#新入生に勧める数学書2018 pic.twitter.com/hmE40vSvBm
杉浦『解析入門』は良い本だと思うけど、位相周りの議論は次々と新しい概念が出てきて混乱しやすく、その辺りは位相空間論の一般論としてやった方が見通し良いと思います。微積・線型の入門書としては齋藤『微分積分学』『線型代数学』(白い本)がバランス良いと思います。 #新入生に勧める数学書2018
— さのたけと (@taketo1024) 2018年3月7日
私が勉強したのもこの本でした。
難しいところがたくさんありますが、普通の本には書いていないけど大事なことがたくさん書いてあります。
数学の力をつけたい人や、授業では分からなかったことを調べるのにもオススメです。
☆解析入門I II (小平邦彦)
私の頃と違って分冊になっちゃったけど、解析は小平邦彦先生の「解析入門」を1回読んでみてレベルを探っていくのは良いんじゃなかろうかと思う。#新入生に勧める数学書2018https://t.co/5X3hub1fmd
— おがわけんたろう (@KentaroOgawa) 2018年3月7日
小平先生はフィールズ賞をとった数学者です。
丁寧に書かれていて、分かりやすさも重視されている本です。
上の三冊が有名ですが、難しい場合には以下の本を紹介している方がいました。
☆解析入門 (ラング)
ラングの解析入門
— オウムガイ (@ougai_quantum) 2018年3月7日
とにかく読みやすい#新入生に勧める数学書2018
レベルが高いようであれば、サージ・ラング先生の「解析入門」を読めば良いかなあ。こっち読むなら演習問題は全部やる方向で。(で良いよね?)#新入生に勧める数学書2018https://t.co/B5GYyxwCVz
— おがわけんたろう (@KentaroOgawa) 2018年3月7日
小平解析や、解析概論、杉浦解析あたりは初めは敷居が高いかも知れない。
— くろもみじ (@mathematica2357) 2018年3月7日
そうなるとラング解析あたりが高校の延長戦としてはいいのでしょうか…。?#新入生に勧める数学書2018
この本自体は、私はちゃんと読んだことがありませんが、ラング先生はたくさんの本を書かれていて、私は"Algebra"をよく読みます。
数学を続けていけば、この本ではなくてもラング先生の本を読むことになるのではないでしょうか。
他にもたくさんの本が紹介されていました。
☆解析入門1-6 (松坂和夫)
https://twitter.com/Annihilated_Uni/status/971243338669215745
☆対話 微分積分学(笠原晧司)
対話・微分積分学―数学解析へのいざない
— 弱いみーくん | itmz153 (@math153arclight) 2018年3月7日
笠原 晧司 (著)
微分積分を学ぶ上で困ったらこの本を読もう.はじめはモヤモヤする極限の話から始まる.
ε-δ論法や実数の連続性もこの本で理解したのかもしれない.
微分積分学の副読本の一つとして最適だろう.
#新入生に勧める数学書2018 pic.twitter.com/wLmiEEbh3p
笠原先生の『対話 微分積分学』を推します!
— Typ (@typtipchip) 2018年3月7日
大学の微積分の講義聴いて「つまらない」とか「よくわからない」と感じたら見てみて欲しいです。
内容は実数の概念についての膝を打つ一言や、テイラー展開の漸近展開として解説、多次元になると分かりにくい陰函数定理など。#新入生に勧める数学書2018 https://t.co/rtUjtVknCW
☆解析学入門(福井常孝/上村外茂男/入江昭二/宮寺功/前原昭二/境正一郎)
#新入生に勧める数学書2018
— mipo (@nekomath271828) 2018年3月7日
「解析学入門」
(内田老鶴圃で出してるやつ)
εδとか一様収束とかなんなんだよ…
数Ⅲでやった微積と極限は、一体なんだったんだよ…
と、泣きそうになったときに読んでました。https://t.co/F244xJSylb
☆解析入門 (田島一郎)
高校と大学の接続という意味で名著だとされています。
— adhara_mathphys (@adhara_mathphys) 2018年3月7日
コンパクトにまとまった解析入門です。
『解析入門』田島一郎#新入生に勧める数学書2018 https://t.co/QlLgcwnAeb
☆イプシロン-デルタ (田島一郎)
"悪名高い"とまで言われるイプシロンデルタ論法を丁寧に書いてある、と個人的に思っている書物。
— とらんせんでんたる (@4294967291prime) 2018年3月8日
微積分を学ぶにあたり、実は∀と∃に悩まされているということ、を乗り越えさせてくれる本なんじゃないかと。https://t.co/lncTqgk8m3
#新入生に勧める数学書2018
ε-δ論法に限って言えば
— 山K (@yamak0523) 2018年3月8日
・田島一郎「解析入門」
・田島一郎「イプシロン-デルタ」
・原惟行、松永秀章「イプシロン・デルタ論法完全攻略」
をおすすめします。
(新入生がいきなりε-δ論法を勉強するのかどうかはおいといて)#新入生に勧める数学書2018
私は読んだことがないのですが、この本は有名ですね。
イプシロンデルタ論法は最近授業で扱われないことも多いそうですが、早いうちに理解できると楽しいです。
(はじめは難しく感じるかもしれませんが、実は難しくないので、数学を勉強しているうちに絶対に理解できます。分からなくても落ち込む必要ないと思います。)
線形代数
線形代数は本当にたくさんの本があります。
基本的には授業で紹介される本を使うと良いと思いますが、それでは分からないと思った時には、評判のいい本や自分の気に入った本を使うと良いでしょう。
☆線形代数入門(斎藤正彦)
#新入生に勧める数学書2018
— ルナ (@Luna13983152) 2018年3月7日
斎藤正彦の線形代数入門です。「具体から抽象へ」というのがよく反映されておりとても読みやすく、また線形代数の基礎がしっかりと固められると思います。
割と本気で選んだ 集合位相と線型代数と代数学は1年の時にめちゃくちゃお世話になった本 初等整数論は今読んでいて程よい行間と問題でB1からでも読めると思う#新入生に勧める数学書2018 pic.twitter.com/9hbhZG3HaM
— ふらすか (@flasca495) 2018年3月7日
#新入生に勧める数学書2018 pic.twitter.com/PuBglY8PNm
— ゴジラ (@gojira_ku) 2018年3月8日
☆線形代数学(佐武一郎)
佐武一郎『線型代数学』、田島一郎『解析入門』、横田一郎『初めて学ぶ人のための群論入門』、田村一郎『トポロジー』。なぜか一郎。#新入生に勧める数学書2018
— yoshitake-h (@yoshitakeh) 2018年3月7日
佐竹先生の『線型代数学』は基礎的なところだけでなく、その発展についての「課題」という形で書いてあります。非常にお世話になっています(現在進行形)
— くろもみじ (@mathematica2357) 2018年3月7日
#新入生に勧める数学書2018
さらに進んだ代数学と多様体論や解析学とのつながりを意識していて論理的厳密性を重視している。線型代数で扱うべきスペクトル分解と双対空間と商空間も書かれてある。この本も長い目で見て何度も役に立つ。
— PDE-M 俊太郎 (@reviewer_amzn_m) 2018年3月10日
3冊とも詳しくはレビュー参照#新入生に勧める数学書2018https://t.co/BlPke4wfSc
やはり、行列が抜けてるのは痛いので春休みから取り掛かるなら2x2行列周りだろうなあ。ということでこの辺り? 別の緑の本はちと硬いよね…
— おがわけんたろう (@KentaroOgawa) 2018年3月7日
#新入生に勧める数学書2018
#新入生に勧める物理学書2018https://t.co/xCs8FXNBdv
☆線形代数学(三宅敏恒)
昨日挙げたやつよりも読みやすいものを挙げた
— ふらすか (@flasca495) 2018年3月8日
#新入生に勧める数学書2018 pic.twitter.com/sSVLOXiFN3
副読本的な本も紹介しておきます。
☆はじめてのリー群
☆はじめてのリー環
井ノ口 はじめてのリー群
— げッドンがッくさばいボッば (@kyow_Q) 2018年3月7日
はじめてのリー環
行列などについての線形代数速習パートがあるので、線形代数の教科書と並行して読むのがよさげ 現代数学で極めて重要な役割を担うリー群などの概念に最速入門できる 線形代数の大切さが、幾何への応用を通してわかるはず#新入生に勧める数学書2018
線形代数は本当にいろんな分野で役に立ちます。
リー群やリー環はその典型例で、これ自体が非常に大切な概念です。
これらの本は線形代数を復習しながら、その使い方も分かるように書かれています。
☆2次行列のすべて
『2次行列のすべて―新しい線型代数の学び方』 石谷 茂
— Loveブルバキ(ラブル) (@lovebourbaki) 2018年3月7日
線形代数の副読本として。2次行列に限定して、線型代数学で学ぶことを一通り学べます。大学の線形代数が抽象的に感じられたらこの本を使うといいと思います。 https://t.co/PO54RUYapV
#新入生に勧める数学書2018
今の高校生は高校で行列を学びませんが、この本は高校の行列で教えられていたことに加えて、大学の線形代数で勉強することを2次行列に限定して一通り勉強できるようになっています。
代数学(整数)
代数学は大学に入ったばかりでは授業がないですが、興味がある人が多いと思います。整数の本もここで紹介しておきます。
☆数論への招待
#新入生に勧める数学書2018
— mipo (@nekomath271828) 2018年3月7日
みんな好きだと思うんですけど、
加藤和也先生の「数論への招待」
高校卒業したての理系の方が、ちょうどよく読めると思います。
そして、加藤先生の見る景色がフワッと見えてきます。
ようこそ、数論へhttps://t.co/kSenzYW3Ko
☆初等整数論講義
☆代数学(雪江 明彦)
神保 道夫著『複素関数入門』(岩波書店)
— 山口 雅司 (@norm_math) 2018年3月7日
(https://t.co/RXWhZ8wT40)
雪江 明彦著『代数学1』(日本評論社)
(https://t.co/6nktEY7Ssw)
を。どちらも初学者に向けて数学の作法、言葉遣いについての丁寧な解説があり、文章が綺麗なので。#新入生に勧める数学書2018
みんな大好きガロアの本も紹介されていました。
☆ガロアと方程式
ガロワと方程式
— 弱いみーくん | itmz153 (@math153arclight) 2018年3月7日
草場 公邦 (著)
ユークリッドの互除法などの初等的な整数論から群論や体論を経て,ガロア理論まで,最短距離で突き進む熱い本.記述も易しい.
5次以上の方程式の解は加減乗除,冪根による公式が存在しないことも証明してある.
連分数の話題も面白い.
#新入生に勧める数学書2018 pic.twitter.com/TP754U570m
☆代数と数論の基礎
☆代数方程式とガロア理論
中島匠一先生の『代数と数論の基礎』はめちゃくちゃ丁寧に書かれているので俺でも読めた(まだちょっとしか読めてないけど『代数方程式とガロア理論』も良さそう) #新入生に勧める数学書2018 pic.twitter.com/DizFk7in6B
— どね( 。•̀_•́。) (@donnay1224) 2018年3月7日
幾何
大学に入ったばかりでは幾何の授業があまりないため、それほど幾何の本は紹介されていませんでした。
しかし、小林昭七先生の以下の本を紹介する人は多かったです。
☆曲線と曲面の微分幾何
どういう人を想定するか難しいですが、数学科の新入生だったら小林昭七先生の「曲線と曲面の微分幾何学」を推したいです。偏微分と2×2の行列を認めて、細かいことを気にしなければ、幾何の面白さが味わえると思います。1章は予備知識も高校の内容だけで読めたと思います◎#新入生に勧める数学書2018
— 松森至宏 (@yoshi_matsumori) 2018年3月8日
この本は具体例が豊富で非常に分かりやすいです。
抽象的な幾何でつまずいている人や幾何に興味がある人はこの本でトレーニングするといいと思います。
これ https://t.co/D5OICVsyaV #新入生に勧める数学書2018
— Lc沢 (@LycoMar) 2018年3月7日
この本は私からもオススメします。
最初、幾何で困ったらこの本を読んでいました、この本以上に頼れる本はないです。
入学したばかりではピンとこないかも知れませんが、頭の片隅に置いておいて欲しいです。
集合と位相
数学科で勉強する集合や位相といった分野は、高校とのギャップが最も大きい分野だと思います。
☆集合・位相入門
#新入生に勧める数学書2018
— タナカ@数学其他諸々で行こう (@MathTanaka2017) 2018年3月7日
・松坂和夫「集合・位相入門」
まあベタですけど.
あと私が書いた
・集合論
松坂の本文で証明省略されて「ムキー(怒)」ってなったら多分これに書いてるはず……という宣伝しとこ(Kindle か DLmarket). pic.twitter.com/zVtNl2RDEa
位相と言えば真っ先にあがる本です。
私もこれで勉強しました。
分かりやすく書いているわけではないですが、丁寧に書かれていて、ゆっくり読めばちゃんと分かるようになっています。
☆集合と位相
こ↑れ↓#新入生に勧める数学書2018 pic.twitter.com/MTVlhmXNdx
— トム (@tom1999_303) 2018年3月7日
松坂『集合と位相』『代数系入門』
— viviちゃん🐰 (@vivich_me) 2018年3月8日
雪江さんの『代数学1 群論入門』
佐武『線型代数』
東大出版の『線形代数入門』と『解析入門』#新入生に勧める数学書2018
この本は分かりやすいとすごく評判の本ですね。
誰にも勧められる本はこれだと思います。
☆トポロジー入門
この本も非常に分かりやすいと評判です。
授業や他の本で挫折した時には是非この本を手にとって欲しいです。
みなさんのアドバイス
本に限らずアドバイスを書いてくださった方もたくさんいましたので、まとめておきます。
ぶっちゃけこのタグ、新入生だけじゃなくても結構ありがたいんですよね…読んだことない本もある本も、身近なレビューとともに参考にできるから。
— くろもみじ (@mathematica2357) 2018年3月7日
まぁ一番大事なのは鵜呑みにしないで実際に自分の目で読んで見ること。先生や先輩、友達と語り合うことなんだろうなぁ…
#新入生に勧める数学書2018
初学者向けの本も大事だけど読んでいくうちに読む力と考える力が育ち概念の本質と広さが分かる本は長い間読めるし理解できたときの喜びは初学者向けの本では味わえない#新入生に勧める数学書2018 https://t.co/8L59h8iwFy
— PDE-M 俊太郎 (@reviewer_amzn_m) 2018年3月10日
#新入生に勧める数学書2018
— mipo (@nekomath271828) 2018年3月7日
数学書と言えば…
神保町の明倫館は絶対知ってた方が良いです。https://t.co/1jDmml4Lbi
正直な所、大学生なら学部1,2年のうちは数学書に限らず人文系含め色々な本を読んどいた方がいいと思うわ。大学出たら社会に放り出されるし、習ったことの使いみちや人生どうやって生きるのかとかも考えねばならないし。#新入生に勧める数学書2018
— waffle (@Space_kid_Jr) 2018年3月7日
その他
上で紹介した枠組みには入らないような本やちょっと変わった本の紹介もありました。いい本ばかりなのでまとめておきます。
☆ 最近、妹がグレブナー基底に興味を持ち始めたのだが。
2017年書泉グランデ数学書第1位!
— グレブナー基底大好きbot (@groebner_basis) 2018年3月7日
グレブナー基底について楽しみながら学んでいくグレ妹、おすすめぶな!#新入生に勧める数学書2018 pic.twitter.com/06FLeP4rFc
カクヨムで連載中の小説の書籍化です。
少しふざけた本のように見えるかもしれませんが、数学の本として本当にいい本だと思います。(私も持っています。)
連載記事は以下で無料で見ることもできます。書籍版は書き下ろしの短編が入っています。
kakuyomu.jp
☆本質から理解する数学的手法
『本質から理解する数学的手法』(定価2,300円)は絶対おすすめ。目次を見ればもうわかると思います。とにかく新入生の痒いところに手が届いています。迷わず買いです#新入生に勧める数学書2018#新入生に勧める物理学書2018 pic.twitter.com/Bsrt39A8np
— AskAboutMathP (@askaboutmathp) 2018年3月8日
この本は知らなかったですが、目次を見たところ、まさに新入生にぴったりの本ですね。
☆数学文章作法 基礎編
『数学文章作法 基礎編』 (ちくま学芸文庫)
— NOGUTAKULab@C94日曜日東フ26b (@NOGUTAKULab) 2018年3月7日
多くの高校生が「文章の書き方」に対して無頓着すぎです(はっきり言って教員レベルでもそうです)。
わかりやすい(≒誤解のない)文章を書くことは、みずからの理解を深めます。そのことを知る良い機会になると思います。#新入生に勧める数学書2018
数学ガールの著者による数学の文章の書き方の本です。
この本も非常にいいです。
☆30講シリーズ
あと、志賀浩二先生の30講シリーズは「何だかよくわからんなぁ…」っとなった時に読むとだいたい何とかさせてくれる。
— くろもみじ (@mathematica2357) 2018年3月7日
イメージや考え方を捉えやすく伝えてくれているので、取り組んでいる数学が肉付きよくなって美味しくなる!!
#新入生に勧める数学書2018
このシリーズを読んで理解できたと言っている人を普段もよく見ます。
授業が分からなくなった時には、このシリーズの本を読むことをお勧めします。
☆マセマシリーズ
誰もすすめてないので私がすすめる。
— Kuto (@GacciDo) 2018年3月7日
マセマ 微分積分と線形代数https://t.co/lpuHIfq9g8https://t.co/9tsSItOiQq
#新入生に勧める数学書2018
問題を解きながら重要な概念を理解していくことができます。
ちゃんとした教科書を買った上でこの本で訓練するといいと思います。
☆数理解析学概論
線型代数も集合も位相も書かれてあり実数論にも詳しく微分法はバナッハ空間において一般的に扱われルベーグ積分もコンパクトにまとまっていて超関数とそのフーリエ変換を厳密に扱っているが他にも色々書いてある
— PDE-M 俊太郎 (@reviewer_amzn_m) 2018年3月9日
長い目で見て何度も役に立つ#新入生に勧める数学書2018 https://t.co/vcEYBYlzaH
大学の数学で勉強する様々な分野がこれ一冊で勉強できます。
とは言え、この本の最大の特徴は解析学の説明です。
解析学の微分方程式への応用は大学の数学でもなかなかたどり着けないのですが、現代数学で非常に重要な部分を占めています。
それを知るには最適な本だと思います。
☆数理論理学
ただし定義などが形式的に若干曖昧なところがあるので数理論理学をちゃんと学びたい場合はこれの後に他の本も目を通すことをおすすめします。
— ちょーさん (@cho_san111000) 2018年3月8日
数理論理学自体を学ぶ目的でなくても自然演繹やヒルベルト流などの形式的証明まででも知っておけば普段の数学でも証明の見通しがよくなるのでおすすめです。
この本は僕が数学を好きになったきっかけの本でもあってオススメしたいところです。
完全性定理や不完全性定理などは聞いたことがあるかもしれませんが、そのようなことも書いています。
Steven H. Strogatz 非線形ダイナミクスとカオス https://t.co/sHC7ILNw3H #新入生に勧める数学書2018 とにかく沢山の非線型現象やカオスに関するトピックに触れられます. 自分で手を動かして (時には計算機を使って) 楽しく読めます.
— srg_bebop (@srg_bebop) 2018年3月7日
力学系の本の中で最も易しく書かれている本だと思います。
力学系自体も面白いですし、解析がどのように応用されるかを知っておくと、発展的な内容を勉強するモチベーションにもなると思います。
☆Lawvereの書籍
https://twitter.com/WatanabeYohei/status/972112043930140672
圏論を知っていると、いろんな分野のつながりが良くわかるようになります。
例をあまり知っていない状態で圏論だけを勉強してもなかなか分かるようにはなりませんが、他の数学と一緒に少しずつ勉強していくと良いと思います。
最近は入門書やネットで読める易しい解説も多く、勉強しやすいと思います。
☆カラー図解 数学事典
『カラー図解 数学事典』
— adhara_mathphys (@adhara_mathphys) 2018年3月8日
きれいな絵や概念図が多く、教科書の副読本として良いと思います。
ただこのようなものを自分で作るとよりためになるとは思います。https://t.co/iIEYr2htrV
#新入生に勧める数学書2018
これも新入生にオススメの本です。
少し高価なので、合格祝いに買ってもらいましょう。
☆LaTeX2ε 美文書作成入門
LaTeXを使えば、数式が綺麗に書けます。
理系ならいつかこの本を買うことになると思います。
☆数学女子
数学女子 1-5 (バンブー・コミックス)
— 弱いみーくん | itmz153 (@math153arclight) 2018年3月7日
安田 まさえ (著)
ゆるふわで生きましょう.
かわいい.#新入生に勧める数学書2018 pic.twitter.com/KzmoitOZlk
数学科の雰囲気が分かる漫画です。